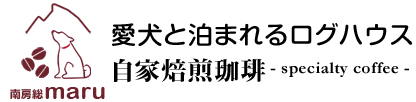自然・歴史・文化
自然
千葉県は、三方を海に囲まれており、夏は涼しく冬は暖かい気候が特徴です。
特に房総半島南部に位置する南房総エリアは都心からも約90分と近く、山や海や里山に囲まれた自然豊かな環境の中で春の菜の花や頼朝桜から冬の水仙まで様々な花が咲き誇り、1年を通じて多くの観光客が訪れています。

【伊予ヶ岳(当施設より車で約3分)】
標高336.6m、房総の山では珍しい岩峯を有していることから千葉県内では唯一山名に「岳」がついており、その姿から「房総のマッターホルン」とも呼ばれております。平群天神社の脇に登山道の入り口があります。
山頂までは大人の足で1時間弱で登れる手軽さの一方、終盤はロープや鎖を伴うため、わんちゃん連れは登山に慣れている子、ケージなどで楽に抱えられる子、もしくは頂上手前の東屋までまでの登頂となります。
【富山(当施設より車で約10分)】
周辺は江戸時代の文豪曲亭(滝沢)馬琴の長編小説「南総里見八犬伝」の舞台となっており、「伏姫籠穴」や「里見八犬士終焉の地」などの見どころも多い山です。1999年には、現在の天皇皇后両陛下もご散策されるなど、比較的ハイキングしやすい山であるため、小型犬などと一緒に登頂される方も良くいらっしゃいます。
山頂からは眼下に岩井の街並みや内房の海など、素晴らしい眺望が360°広がります。


【岩井海岸(当施設より車で約15分)】
南北に約2㎞の弓場の砂浜が広がる岩井海岸は、内房エリアにありながら、東京湾の入り口より南の外洋に突き出しているため、比較的透明度も高い海です。
遠浅で波も静かなことから、お子様や小学校の臨海学校で人気の海岸で、砂浜もとても広いためわんちゃんとお散歩する姿も良く目にすることができます。
特に、海に沈んでいく綺麗な夕日は圧巻です。
【大山千枚田(当施設より車で約15分)】
鴨川市の嶺岡の山並みの麓にあり、東京から一番近い棚田として知られ、1999年7月には「日本の棚田百選」に認定されております。
階段状の大小375枚の田んぼが連なっている日本で唯一雨水のみで耕作を行っている天水田で、その他洪水などの災害を防止したり、貴重な生態系や環境の保全になる等多面的機能も有しております。
稲の成長に合わせて鮮やかな緑色~黄金色へと、季節ごとに異なる魅力をわんちゃんと散策してみてはいかがでしょう。


【とみやま水仙遊歩道(当施設より車で約10分)】
お隣の町である鋸南町の特産物として知られる日本水仙は、江戸時代には房州から船で江戸に出荷され、「元名(もとな)の花」と高貴な花として好評を得ました。
例年1月の寒い時期~見ごろを満開を迎えますが、満開の水仙の間をわんちゃんと進んだ先には展望台があり、岩井の街並みや内房の海を臨むことができます。
その他施設より車で約30分圏内


歴史・文化
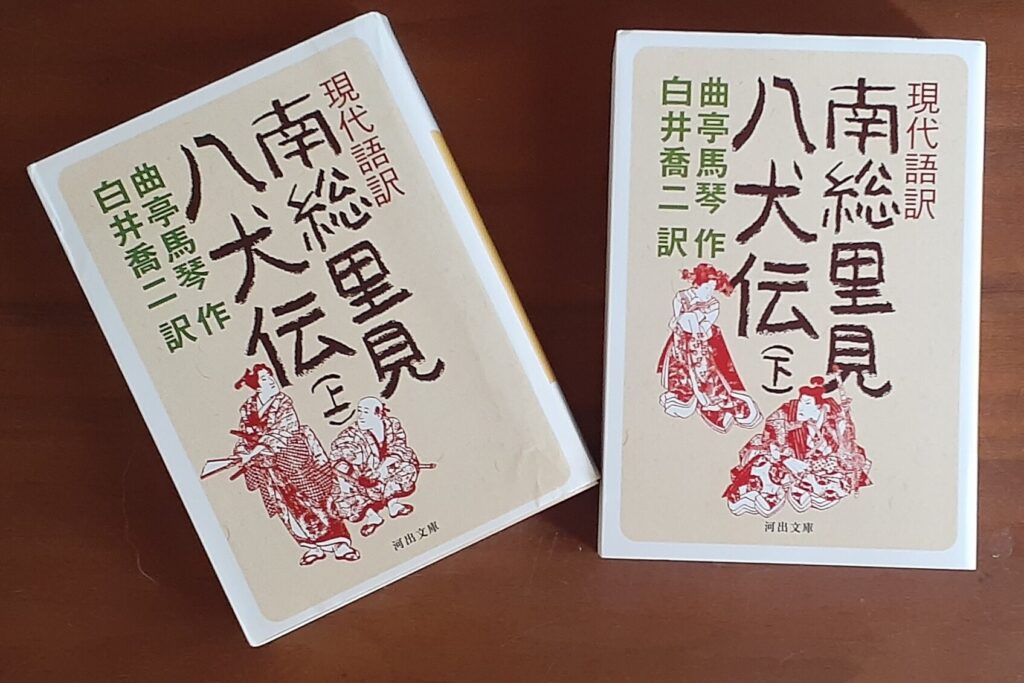
【南総里見八犬伝ゆかりの地(当施設から車で15分圏内に点在)】
戦国時代以降、安房地域は源氏を祖とする里見氏が10代170年ほどにわたり支配しましたが、後に江戸幕府より改易を命じられて断絶させられる悲しい歴史を持っています。
江戸時代の文豪曲亭(滝沢)馬琴が1814年(文化11年)から1842年(天保13年)まで、何と28年もの年月をかけて著した全98巻106冊の長編小説である「南総里見八犬伝」は、その里見氏の歴史を題材に創作されたもので、南房総の中でも富山エリアが舞台の中心に描かれており、周辺には里見氏の古戦場や、物語に登場する伏姫や八房、八犬士にちなんだ場所が点在しています。
【日本酪農発祥地(当施設より車で約15分)】
・「千葉県酪農のさと」※ペット同伴不可
・「みねおかいきいき館」
南房総の嶺岡一帯は、戦国時代に里見氏の軍馬育成のための牧場を、江戸時代に幕府が直轄管理し、享保の改革で有名な8代将軍徳川吉宗が享保13年(1728年)インド産といわれる白牛3頭をこの嶺岡牧で飼育。
そこで疲労回復の強壮剤や薬などとして用いた「白牛酪」という乳製品がつくられ、千葉県が日本酪農発祥地として「千葉県史跡」に指定しています。
日本酪農発祥の地で販売されてソフトクリームは絶品です。

※各観光地の場所や詳細情報は、
「周辺マップ」のページをご活用下さい